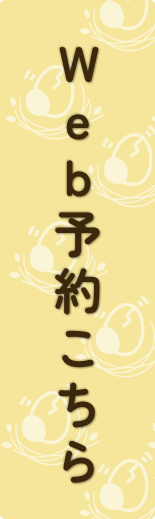沖縄県の不登校と発達障害のお子さんのための家庭教師、家庭教師のハッチのブログに来てくださってありがとうございます。
今日は臨床心理士として教育委員会やスクールカウンセラーをしていた私が家庭教師の仕事を始めたいと思った理由についてお話しします。
独立して自分でお仕事をしてみたいな、子育てしながらなにができるかな、と考えていた私が家庭教師を始めようと思った理由
まず1つめは自己肯定感を高めてあげるかかわりが、お勉強を通してできると思ったから。
家庭教師のハッチを立ち上げる前に「不登校の子どもに合う家庭教師を知っていませんか?」と尋ねられることがしばしばありました。
不登校のお子さんを持つ親御さんが、学校に行くのは難しいし、地域の塾にも同じ学校の友達がいて顔を合わせるのは嫌みたいだし、じゃあ家庭教師はどうだろう?と考えられるのは、とても自然な流れなのかなと思います。
学校の勉強がどれほど生きていくのに役立つかはさておき、不登校のお子さん自身も「勉強しなくて大丈夫なのかな」と不安に思っていることは多くあるように思います。
勉強のいいところは、大きなはなまるをお子さんの頑張りにつけてあげられるところだと思うのです。
「自己肯定感を育てましょう」と言われることが多くありますが、じゃあ一体どうやって、の答えはあいまいですぐに効果が実感できるものでもありません。
でもはなまるをもらって自己肯定感が上がらないお子さんはいないと思うのです。
たくさんはなまるをあげて、たくさん褒めてあげられる。超シンプルだけど一番大事にしていることです。
ところで、「臨床心理士はカウンセリングで、自己肯定感を高めるようなことができるんじゃないの?」という疑問がわく保護者の方もいらっしゃるかなと思います。
「なんで家庭訪問カウンセラーじゃなくて、家庭教師なの?」と。
別に聞かれたことはないので、誰も思ってないのかもしれないのですが、私なりの理由があるのでお伝えしたいです。
カウンセリングをするためにとっても大切なことがあるよ、と私は臨床心理士になるための大学院時代に習いました。
それは、カウンセリングをする場所が「安全で、守られた、特別な場所であること」。
カウンセリングルームに入る。「ここは自分の心を開いてお話する特別な場所だ」と思う。
カウンセリングは、つらい気持ちをお話したり、泣いたり怒ったり、自分ってこんなに嫌な奴だったのか、みたいなことに気づいてしまったり、結構ネガティブな部分もあります。
カウンセリングを受けたからこそ落ち込むこともある。
でもそうは言っても日常生活を送っていかなきゃならない。
カウンセリングルームを出たら気持ちを切り替えて日常に戻っていく。
だからカウンセリングルームは「安全で、守られた、特別な場所」じゃないといけないんだよ、と。
お子さんにとってお家は、一番安全で、一番守られた場所だけど、そこは日常の大切な場所。だから心の奥を見つめなおすようなカウンセリングには向いていません。
私たちはカウンセリングはあえてしませんが、子どもたちとおしゃべりをして仲良くなって、笑顔を増やしてはなまるをいっぱいつけられる、専門的な知識でお子さんと親御さんを支えられる、そんな家庭教師を目指しています!
きっかけ②に続きます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
沖縄県で不登校と発達障害のお子さま専門の家庭教師、家庭教師のハッチでした。
お問い合わせは予約フォームが便利です。お気軽にお問い合わせください!