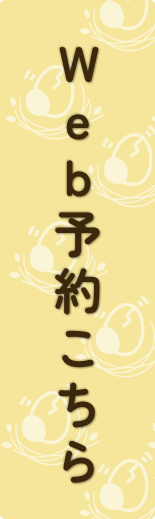こんにちは。代表臨床心理士の松川さやかです。
沖縄県の不登校と発達障害のお子さんのための家庭教師、家庭教師のハッチのブログに来てくださってありがとうございます。
今日は私、代表臨床心理士の松川さやかの自己紹介の続き③です。
教育委員会関係でお仕事をしたことがある臨床心理士が夏になるとてんてこまいになるお仕事があります。
「特別支援学級に入るかどうかの判定をする知能検査の検査員」です。
教育委員会の中でも、不登校のお子さんを担当する教育委員会の係と、特別支援(障害がある/発達障害)のお子さんを担当する教育委員会の係は別です。
役所の中で、階が違ったり、建物自体が違ったりします。(同じところもあります)
特別支援の係に勤めていたことはありませんが、検査員としてはお仕事をさせていただいています。
自分のお子さんが、特別支援学級を利用した方がいいのかもしれない、と思った場合、入るまでには結構長い時間がかかります。
どんな子が入るものなのか。どんな手続きが必要なのか。支援学級にはどんなメリットが、デメリットがあるのか。
大まかな仕組みと時間の流れ、そしてメリットデメリットについても、お話できるのは私の強みかなと思います。
家庭教師のフォローアップだけでくらいついていけるのか、支援学級に入った方が伸びるのか。
あるいは中学生になると支援学校に在籍することでプリントのもらい損ねや提出物のモレなどが出てきてしまうのでそこをどう捉えるのか。そんなことも相談にのらせていただいています。
長くなりましたが、私の経験してきたお仕事を自己紹介としてお伝えしました。
今後は、家庭教師を始めた理由や、家庭教師として心掛けていることなどについてもお話していけたらと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
沖縄県で不登校と発達障害のお子さんのための家庭教師、家庭教師のハッチの臨床心理士松川さやかでした。